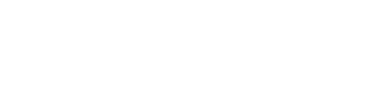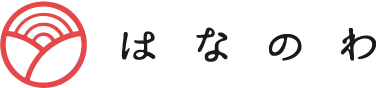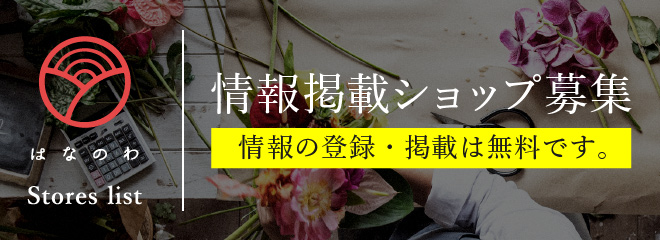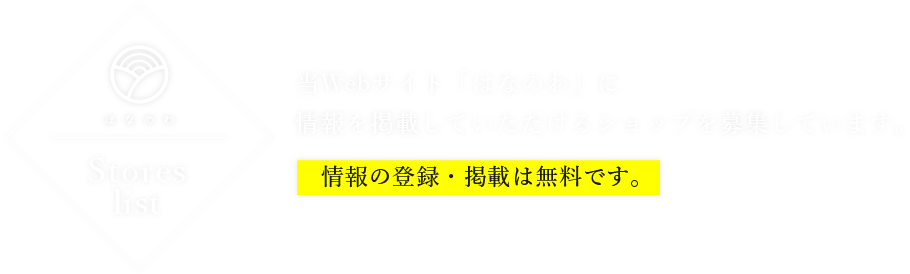これで鶏胸肉がパサつかない!しっとり柔らかくする方法
記事の監修
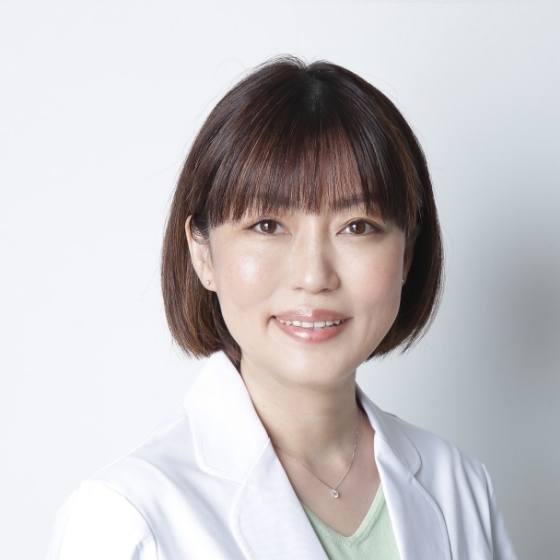
福光 佳奈子
漬け込み酒マイスター・ECサイト「イエノミライフ」運営
札幌市生まれ。
大学卒業後、広告会社やメーカーに勤務。会社員時代より漬け込み酒作りをはじめ、これまでに1,000種類を超える漬け込み酒レシピを開発。
現在は、食や健康に関する執筆や監修、セミナー講師などをしている。
麦焼酎「いいちこ」を使ったレシピ開発も多数手がける。
著書「体にうれしい果実酒・野菜酒・薬用酒200」(秀和システム)は、台湾やシンガポールなど世界5か国で翻訳版も出版。女性セブン、AERA、FLASH、Yahoo!ニュース、日本経済新聞など取材実績が多数ある。
保有資格は、野菜ソムリエプロ、薬膳インストラクター、睡眠コンサルタントほか。
鶏胸肉はあっさりとしていて食べやすいですが、加熱するとパサパサになってしまうことも少なくありません。柔らかく美味しく調理するには、ちょっとした工夫が必要です。リーズナブルでさまざまな料理に使える鶏胸肉はとても便利な食材。より美味しく調理するコツを知っていれば、さらに献立に取り入れやすくなりますよ。
そこで今回は、鶏胸肉を柔らかくする方法をご紹介します。調理の際にひと手間加えるだけで、いつもの鶏料理がもっと美味しく仕上がります。難しい作業は一切ありませんので、ぜひ気軽に取り入れてみてくださいね。
- 鶏胸肉をより美味しく調理する方法を知りたい方
- いつも鶏胸肉がパサパサになってしまうという方
- リーズナブルな食材で美味しい料理を作りたい方
目次
鶏胸肉を柔らかくするには

鶏胸肉は食肉のなかでも比較的脂質が少なく、さっぱりとした味わいが特徴です。クセが少なくて比較的低価格なため、たんぱく質を気軽に摂れる食材としても人気がありますね。その反面、加熱するとパサパサとした食感になりがちで、ジューシーさに欠けるという難点も。これは、鶏胸肉の筋原線維たんぱく質とコラーゲンが加熱により収縮することと、それに伴い肉汁が流出してしまうことが原因です。
長時間の煮込み料理は例外ですが、一般的な炒め物などの場合は加熱が進むにつれ硬くなってしまいます。
そのため、鶏胸肉を柔らかくするには、筋繊維の収縮と肉汁(水分)の流出を防ぐことが重要なのです。筋繊維を断ち切ったりほぐしたりする下処理や、保水性をキープするような加熱の仕方がポイントとなります。
- 筋繊維を断ち切る(ほぐす)ための下処理を行う
- 肉汁の流出を防ぐための下処理を行い、加熱の仕方を工夫する
上記の2つのポイントを踏まえて、鶏胸肉を柔らかくする方法を具体的にご紹介していきます。
筋繊維を断つ切り方

鶏胸肉の筋繊維は加熱により縮みますので、下処理で繊維を分断しておきましょう。繊維質な部分が細かく切れていれば、加熱で縮んだとしてもパサパサした食感にはなりにくいです。手軽に筋繊維を断つには、「そぎ切り」と「フォークで刺す方法」のどちらかの下処理を行うといいでしょう。
鶏胸肉をひと口大に切り分けて調理するならそぎ切り、チキンステーキなど丸ごとの状態で調理するならフォークで刺す方法がおすすめです。それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。
そぎ切り
そぎ切りは、包丁を使って鶏胸肉の繊維と垂直になるように切っていく方法です。生の鶏胸肉だけでなく、1枚肉の蒸し鶏や茹で鶏、ステーキなどを切り分ける際にもおすすめの切り方ですよ。食感が柔らかくなるだけでなく、見た目もきれいに仕上がります。
手順
-
STEP. 1
鶏胸肉1枚を皮を下にして広げて、大まか(3等分くらい)に切り分ける
-
STEP. 2
切り分けた鶏胸肉を、それぞれ繊維が包丁と垂直になるように置く
-
STEP. 3
包丁の刃を斜めに寝かせて、肉の繊維を断ち切りながらそぐように切っていく
-
STEP. 4
完成
そぎ切りにする際に厚みを調整することで、さまざまな料理に使えます。炒め物や親子丼の具、唐揚げなどの料理に合わせて、大きさや厚みを好みで調整するといいでしょう。上記の方法では3つに切り分けてからそぎ切りしていますが、大きめに使いたい場合は1枚をそのままそぎ切りしてもOKです。
下記の動画では、そぎ切りの方法をご紹介しています。参考にしてみてください。
フォークで刺す方法
1枚肉をそのまま調理したい場合は、鶏胸肉全体をフォークで刺して筋繊維を断ち切りましょう。その際、皮が縮まないように皮の部分も一緒に刺して全体に細かく穴を開けるのがポイントです。そぎ切りとは逆に、皮目を上にした状態で刺してください。
フォークで細かく穴を開けることにより鶏胸肉が柔らかくなるだけでなく、火が通りやすくなる、味がしみやすくなる(下味をつける場合)というメリットもあります。
ただし、鶏胸肉の場合は叩くことで逆に肉汁が出てしまいやすいため、あまりおすすめできません。包丁の背で軽く叩く程度にしておきましょう。
漬け込む方法

鶏胸肉を調味料など他の食品に漬け込んでから加熱するのも、柔らかくする方法の一つです。漬け込む食品の種類によって、筋原線維たんぱく質をほぐす、加熱による変質を遅らせる、保水性を高めるなど、効果はさまざまです。ここからは、効果の期待できる代表的な食品をご紹介していきます。
塩麹
発酵調味料の塩麹は、下味に使うと肉や魚が柔らかくなり美味しいと一時期ブームを引き起こしましたね。これは、たんぱく質を分解する働きのあるプロテアーゼという酵素により、筋原線維たんぱく質やコラーゲンがほぐれるからです。塩麹そのものの風味で下味も付き、肉も柔らかくなるため時短調理にも最適といえるでしょう。
プロテアーゼの効果を目的に使うなら、非加熱のものを選びましょう。
塩麹の他にも、パイナップルや舞茸、生姜などプロテアーゼを含む食品はたくさんあります。これらを活用して鶏胸肉を柔らかくする方法も試してみてはいかがでしょう。パイナップルや生姜のしぼり汁にそぎ切りした鶏胸肉を漬け込んでから加熱することで、効果が期待できます。
参考元:広島県 米麹の利用方法
宝酒造株式会社 魚、肉の食感
ブライン液
どこの家庭にも常備してある調味料で簡単に作れるブライン液もおすすめです。作り方は、砂糖と塩を水に溶かすだけととても簡単。水100mlに対し砂糖小さじ1と1/2、塩小さじ2/3がおすすめの配合です。ブライン液とはアメリカでの呼び方で、フランスではソミュール液、日本でも塩糖水と古くから用いられてきたのだとか。
砂糖には、たんぱく質と結びつき加熱による変性を遅らせる働きや、水分保持効果があるといわれています。また、塩には塩素イオンにより筋原線維を膨潤させ保水性を高める効果があるそうです。これらの2つの働きが合わさることで、鶏胸肉などの肉や魚を柔らかくすることができるのです。
ブライン液に漬けた状態で鶏胸肉を冷蔵保存することもできます。日をまたいで保存する場合はブライン液を毎日取り換えて、4日以内を目安に調理しましょう。
漬け込む場合の注意点
他にも、アルコールに漬けて柔らかくする方法などもあります。料理酒は唐揚げの下味にも一般的に使われますので、なじみのある方法ですね。酒に漬けてから調理することで、味がしみ込みやすくなるだけでなく、肉の保水性を高める効果も得られるのです。ただし、塩や醤油を使う場合は、漬け込み時間が長くなり過ぎないように気を付けましょう。
塩には食材の水分を外に出す働きがあります。魚の振り塩やきゅうりの塩もみでは、その作用を利用することで余分な水分を取り除けますね。鶏胸肉の場合は、塩や塩分を含む醤油に漬け込み過ぎると水分が出てパサパサになってしまうため、注意が必要なのです。酒や生姜だけなら問題ありませんが、塩の強いものに漬け込む場合は短時間に留めてくださいね。
コーティングする方法

鶏胸肉の表面をコーティングしてから加熱するのも、柔らかくする方法として効果的です。唐揚げや竜田揚げにする場合は一般的に行われますが、炒め物などにする場合もコーティングしておくと美味しいですよ。これまでご紹介した方法で筋繊維を断ち切ったり保水性を高めたりしても、加熱で水分が流出してしまったら台無しに。それを防ぐためにも、コーティングはぜひおすすめしたい方法です。
特に、細かくカットした鶏胸肉を柔らかく加熱するのは至難の業。あらかじめコーティングしておくことで水分の流出を防ぎましょう。簡単にできる基本の方法をご紹介します。
片栗粉や小麦粉をまぶす
最も一般的なのは、片栗粉や小麦粉を鶏胸肉にまぶす方法です。例えば唐揚げの場合、片栗粉のみでコーティングするとサクッと軽い食感に、小麦粉のみではガリッとしたやや重めの食感に仕上がります。おすすめなのは、両方を混ぜ合わせてまぶす方法。片栗粉と小麦粉のいいとこどりができて、軽さと歯ごたえを兼ね備えたほどよい食感に仕上がりますよ。
いずれの場合も、簡単にまぶしたいならビニール袋を使うのがおすすめ。カットした鶏胸肉と粉をビニール袋に入れて空気を含ませてから口を閉じ、下から手で軽く持ち上げるようにして振るとまんべんなくまぶすことができます。
表面に味がしっかりと付くため、より美味しく仕上がりますよ。
卵液にくぐらせる
肉に卵液を絡めてから焼く料理はポークピカタが有名ですが、鶏胸肉にも応用できます。鶏胸肉をそのまま卵液にくぐらせてから焼いてもいいですが、小麦粉をまぶしてからくぐらせるとより効果的。粉と卵液でコーティングすることで、しっとりふっくらとした食感に仕上がりますよ。
塩こしょうで下味を付けてから調理するのが一般的ですが、卵液に粉チーズやパセリなどを混ぜておくのもおすすめ。好みでアレンジしましょう。卵液を使えばただ焼くだけでも立派なおかずになりますので、時短調理したいときにも便利な方法です。
ケチャップをかけて食べるのがおすすめです。お弁当のおかずにも役立ちますよ。
加熱の仕方

鶏胸肉は加熱が進むにつれて水分が流出しやすくなってしまいます。パサパサした食感になるのを防ぐためには、加熱の仕方にも工夫が必要。そこで、ここからは鶏胸肉を柔らかく仕上げるための加熱のポイントについてお伝えしていきます。火の入れ方だけでなく加熱する前の段階からもコツがあるため、しっかりと押さえておきましょう。
- 肉を常温に出してから加熱する
- 加熱時間をできるだけ短くする
- 余熱を利用する
上記の3点を踏まえて加熱することで、パサつきの主な原因である「加熱し過ぎによる水分の流出」を防ぎましょう。具体的にどのようにすればいいか解説していきます。
常温に出してから加熱する
鶏胸肉を冷蔵庫から出してすぐに加熱すると、肉の表面温度と中心温度の差が大きくなり、加熱ムラができやすくなってしまいます。その結果、中心部まで火を通すために加熱時間が長くなり水分が抜けてパサパサの食感に。そこで、1枚肉をそのまま焼くなど厚みのある肉の場合は、冷蔵庫から出して30分程度置いてから加熱するのがおすすめです。これは、鶏肉だけでなくほかの厚切り肉や魚などでも同様です。
下処理でそぎ切りにしたり漬け込んだりする場合は、その作業を行っている間に自然と常温に戻りますし、薄切りや小さくカットしたものは温度差も少ないためそのまま加熱して問題ありません。厚みのある肉や魚の場合は、温度変化を和らげるために常温に戻してから加熱するといいでしょう。
気温・室温の高い時期は10分程度出しておくだけでも常温に戻ります。
漬け込んでから加熱する場合も、漬け込みが1時間以上になる場合は常温ではなく冷蔵庫で行いましょう。
また、鶏胸肉は厚みが均一ではないことも加熱ムラの原因となります。そぎ切りにしたり開いたりして厚みをある程度整えておくことも、加熱し過ぎを防ぐのに効果的です。
長時間加熱し過ぎない
加熱時間を短くするには、調理の手順も重要です。鶏胸肉だけを調理する場合は短く切り上げればいいだけなので簡単ですが、野菜など他の食材と炒め合わせる場合などは、工夫が必要。一般的には肉→野菜という順で加熱して最後に味付けをすることが多いですが、野菜などでも火の通りにくい食材があると、加熱時間が長引いてしまいますよね。
そこで、鶏胸肉を炒めて火が通ったら、面倒でも一旦お皿などに取り出しておく方法がおすすめです。その後、野菜など他の食材を炒めて、最後に鶏胸肉を戻し入れて味付けしましょう。そうすることで、加熱し過ぎによる肉のパサつきを防ぐことができますし、他の食材もほどよい食感に仕上がります。
余熱を利用する
加熱調理では、火のついている間に火を通さなければ…と思いがちですが、余熱でも意外と火は入ります。そのため、しっかりと火を通そうとした結果、加熱し過ぎになるケースは少なくありません。鶏肉の場合は中心部まで火を通す必要がありますが、火を消す直前にしっかりと温度が上がっていれば、余熱が十分活用できます。パサつきを防ぐには、余熱も計算しながら調理するのがベストなのです。
- 茹で鶏:火を止めてから蓋をした状態で、30分以上置いておく
- 蒸し鶏(電子レンジ調理):加熱後、蒸し汁ごとラップをかけたまま冷ます
- 焼き料理:加熱後、オーブン・グリル内、フライパンで2分程度置いておく
余熱でじわじわと火を通すことで、しっとりとした食感の鶏胸肉に仕上がりますよ。加熱時間に不安がある場合は、余熱で火を通すことも取り入れてみてくださいね。
適切な加熱時間は調理器具や肉の厚みによっても異なります。カットして断面をチェックして、生焼けになっていないことを確かめることが大切です。
低温調理もおすすめ

筋原線維たんぱく質は、高温になるほど収縮しやすくなり、水分も流出しやすくなります。そのため、水分の流出を防ぐには低温でじっくり加熱する調理法が効果的です。低温調理なら、筋繊維のカットや漬け込みなどの下処理を行わなくても、水分が保持されたまま加熱されるため、簡単に柔らかくてジューシーな鶏胸肉に仕上げることができます。
ただし、一般的な家庭の調理器具で温度を一定に保ちながら確実に火入れを行うことは至難の業。自己流の低温調理は、食中毒のリスクも高いためおすすめできません。低温調理に挑戦したい場合は、専用の調理器具を用いる方法で安全・確実に行いましょう。
専用の低温調理器には劣りますが、炊飯器も温度を一定に保つことができます。下処理を行った鶏胸肉を炊飯器で加熱調理すれば、美味しい茹で鶏を簡単に作ることも可能です。
まとめ
鶏胸肉がパサパサになってしまうのは、加熱により筋原線維たんぱく質が収縮し水分が流出するからです。そのため、筋繊維の収縮をできるだけ防ぎ水分の流出を抑えることが、鶏胸肉を柔らかくする方法のカギとなります。
筋繊維を包丁やフォークで断ち切る方法、酵素や砂糖、塩の働きを利用して筋繊維をほぐし保水性を高める方法、鶏胸肉の表面をコーティングする方法など、下処理だけでもそのやり方はさまざま。好みの方法を選んでもいいですし、併用すればより効果が期待できるでしょう。
また、これらの方法に加えて、加熱し過ぎないことも水分の流出を防ぐには重要なポイントです。温度変化を和らげるために、鶏胸肉を常温に戻してから加熱し余熱も活用しましょう。火加減が難しい場合は低温調理器の利用も確実な方法です。柔らかくする方法はさまざまですので、取り入れやすいものをぜひ試してみてくださいね。
- 鶏胸肉を柔らかくする方法のポイントは、筋原線維たんぱく質の収縮と水分の流出を防ぐこと
- 筋繊維を断ち切るか緩める・保水性を高める下処理(切り方の工夫や漬け込み、コーティング)が効果的
- 加熱し過ぎを防ぐために、鶏胸肉の温度調整や余熱の利用、加熱手順の工夫、低温調理などを取り入れてみよう
記事の監修
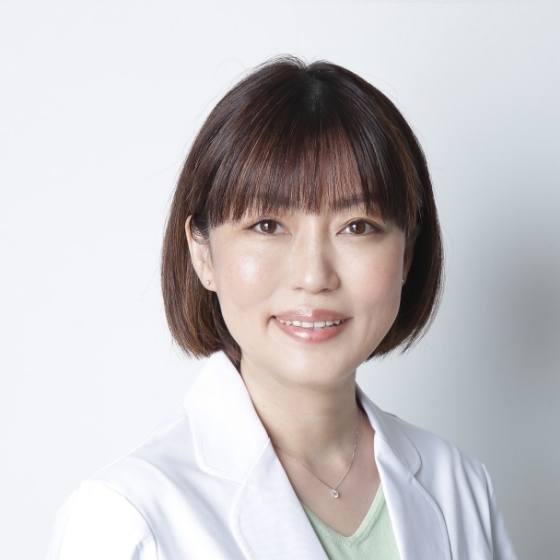
福光 佳奈子
漬け込み酒マイスター・ECサイト「イエノミライフ」運営
札幌市生まれ。
大学卒業後、広告会社やメーカーに勤務。会社員時代より漬け込み酒作りをはじめ、これまでに1,000種類を超える漬け込み酒レシピを開発。
現在は、食や健康に関する執筆や監修、セミナー講師などをしている。
麦焼酎「いいちこ」を使ったレシピ開発も多数手がける。
著書「体にうれしい果実酒・野菜酒・薬用酒200」(秀和システム)は、台湾やシンガポールなど世界5か国で翻訳版も出版。女性セブン、AERA、FLASH、Yahoo!ニュース、日本経済新聞など取材実績が多数ある。
保有資格は、野菜ソムリエプロ、薬膳インストラクター、睡眠コンサルタントほか。