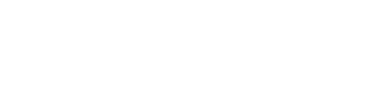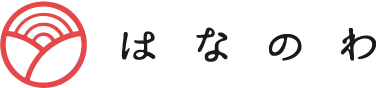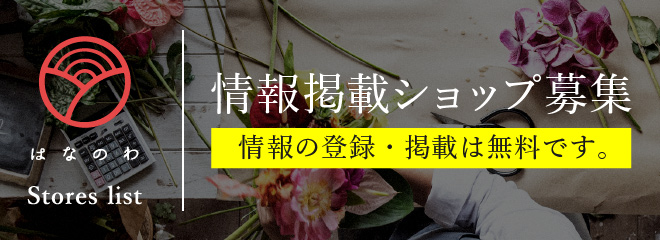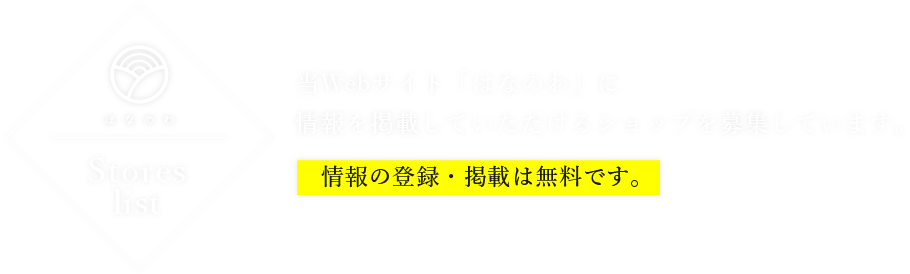エアプランツの基礎知識を学んで楽しく育てよう!長持ちする育て方のポイント
インテリアにおしゃれにグリーンを取り入れたい人々から人気を集めているエアプランツ。ユニークな見た目と管理のしやすさがポイントで、植物を育てるのが苦手な人でも気軽にインテリアに取り入れることができます。エアプランツは、植物の中でもちょっと変わった特徴があり、お世話の仕方も他の植物とは違います。
そこで今回は、そんな不思議な植物・エアプランツについての基本的な知識や育て方のポイント、そして飾り方のアイデアをご紹介します。エアプランツとはどんな植物なのか、一緒に探っていきましょう。
- エアプランツに興味がある方
- エアプランツの生態や自宅での上手な育て方を知りたい方
- エアプランツをおしゃれに飾ってみたい方
目次
エアプランツとは

そもそもエアプランツは、パイナップル科の多年生植物チランジア属の仲間で、数百種類以上あるといわれています。チランジアの中から市場に出回るようになった一部がエアプランツと呼ばれるようになったそうです。
その生息地はさまざまですが、代表的なのはアメリカ南部からメキシコに広がる砂漠地域と、ブラジル・コロンビアなどの熱帯雨林地域の2つ。いずれも植物にとっては苛酷な環境といえます。
そんな場所でも生きていけるのは、他の植物とは違って、根からではなく葉から水分と栄養分を吸収しているから。独特な生態のなせる技ですね。
砂漠地域に育つものは銀葉種、熱帯雨林に育つものは緑葉種と呼ばれ、この2種類はそれぞれ見た目も好む環境も異なります。詳しく見ていきましょう。
銀葉種と緑葉種

銀葉種のエアプランツは、白っぽい見た目が特徴的。これは、強い日光と乾燥という厳しい環境で生き抜くために、水を取り込む器官であるトリコームと呼ばれる無数の毛で覆われているためです。銀葉種でよく見られる品種には、エアプランツの代表格とも言えるキセログラフィカや、葉がカールしたりシュッと伸びたりするストレプトフィラ、人気のジュンセアやイオナンタなどがあります。
一方、緑葉種は熱帯雨林に生息しているためトリコームは少なく、葉はつやつやとした緑色です。銀葉種とは逆の湿度の高い環境を好み、日差しには弱い種類です。3色の花が咲くトリコロール、まだら模様の葉が長く伸びるブッツィー、そしてブルボーサ、ブラキカウロスなどが有名です。
エアプランツは種類が豊富

生息地によって特徴や生態の異なるエアプランツですが、非常に種類が多い植物でもあります。先ほどもお伝えしましたが、エアプランツはチランジアの一部の通称です。チランジアの中のどこまでをエアプランツと呼ぶかという明確な線引きもありません。そう考えると、チランジア自体は数百種類存在するため、エアプランツの種類も相当な数になるでしょう。
実際、日本の市場に出回っているエアプランツはほんの一部にすぎません。やはり日本の気候と生息地の気候が異なりますので、すべてのエアプランツを日本に持ち込むことは難しいのかもしれませんね。
エアプランツは「着生植物」

エアプランツの基礎知識としてあまり知られていないのが、エアプランツが「着生植物」であるということです。生息地では、エアプランツの多くは樹木などに種が貼り付付き、根を伸ばして自身を固定します。これを着生(ちゃくせい)と言い、中にはサボテンや岩などに着生するものもあります。
エアプランツの根は「気根」と呼ばれます。一般的な植物の根は土の中で伸び、栄養や水分を吸収する働きをしますが、エアプランツの根はそのような働きはしません。ただ単に他の自然物にくっつくためだけの役割と言われています。
ですが、園芸店によっては、根を伸ばして着生させた状態で販売されていることもあります。
エアプランツの選び方

エアプランツは非常に種類が豊富なため、どのように選べばよいのか悩んでしまうかもしれません。エアプランツは園芸店のほか、最近ではホームセンターやインテリアショップ、さらに100円ショップなどでも販売されるようになりました。店頭でエアプランツを選ぶ際の見分け方や、初めて育てる方でも扱いやすいおすすめの品種についてご紹介していきます。
初心者でも育てやすいおすすめの品種

初めてエアプランツを育てる方にとっては、管理が簡単な扱いやすい品種、生長がわかりやすく育てる楽しみを実感しやすい品種を選ぶのがおすすめです。銀葉種と緑葉種から、初心者の方にもおすすめの品種をご紹介しましょう。
- コットンキャンディー:生長するとピンク色の花が咲く。子株がつきやすく増やして楽しめる
- ベルゲリ:長く伸びながら育ち、薄紫色の花が咲く。子株がつきやすく、耐寒性が非常に高い
- キセログラフィカ:エアプランツの王様といわれる品種。大きめで美しいカーブの葉が特徴
- イオナンタ:生長が早く、細長い葉が伸びる。紫や白の花を咲かせるもの、葉がピンクに変わるものなどもある
- テクトラム:トリコームが長く、ふわふわとした優しい印象。ソーキングが不要
- ブラキカウロス:緑葉種の定番品種で生長が早い。放射状に伸びる薄い葉が特徴で、開花時には赤く染まる
- ブルボーサ:壺型の個性的なフォルムとうねりのある葉が特徴。子株がつきやすく増やして楽しめる
- トリコロール:赤や黄色の花苞と紫色の花が咲く。葉の先が尖っているため管理には注意が必要
- キアネア:花の鑑賞を楽しめる品種。ピンクの花序から紫色の美しい花が咲く
- フィリフォリア:葉が細く繊細な印象の品種で、10個以上の花序に花が咲く。高温に弱く蒸れに注意
エアプランツ自体が扱いやすい植物ですが、上記の品種は特に扱いやすく育てる楽しみも得やすいです。葉が伸びる品種、美しい花を咲かせる品種、姿形がユニークな品種など、個性豊か。好みのものを探す時間もぜひ楽しみましょう。
失敗しない選び方のコツ

エアプランツは管理の仕方によって、状態がかなり変わってきます。そのため、店頭で実際にエアプランツを手に取って見ることができる場合は、株の状態をしっかりとチェックすることをおすすめします。主なチェックポイントは、株全体の葉の色、持ったときの重量感です。お店でしっかりと管理されているものとそうでないものには、下記のような違いが出てきます。
- 葉の色:株全体がきれいな色をしているものを選ぶ。状態が悪いものは、変色やくすみが見られる
- 重量感:持ったときに適度な重みを感じられるものを選ぶ。軽すぎるものは、水分不足で乾燥している
- その他:表面にシワがある、柔らかすぎるものは水分不足で傷みやすいため避ける。害虫の有無もチェック
より長くエアプランツを楽しむためには、購入時に状態のいいエアプランツを選ぶことが大切です。また、同じ品種であれば大きめの株のほうが丈夫で育ちやすいといわれています。特に初心者の方は、やや大きめの株を選ぶといいでしょう。
エアプランツの育て方

エアプランツは空気中の水分を吸って育つ植物といわれ、それがこの通称の由来でもあります。でも、本当に空気中の水分だけで育てることができるのか疑問に思う人もいるのではないでしょうか?
エアプランツの生息地である熱帯地域は湿度が高いので、空気中の水分を十分に吸収して育つことができます。また、砂漠でも日中と夜間の気温差により発生する霧から水分を補給できるので育つのです。
水やりも含め、エアプランツを順調に育てるために知っておくと役立つポイントがいくつかあります。1つずつご紹介します。
独特の水やりの仕方がポイント

エアプランツは根が土に埋まっていないので、水やりの方法は独特です。基本的には「ミスティング」と「ソーキング」の2種類の方法があります。
まず、「ミスティング」は、霧吹きを使って行います。葉全体にいきわたるようスプレーしましょう。頻度は週2回ほどです。また、水やりをする時間は夕方以降が原則です。なぜなら、エアプランツは昼間は気孔が閉じていて水分を吸収できないからです。
次に「ソーキング」ですが、こちらはエアプランツを水に浸して4~6時間ほど置いておく水やり方法です。乾燥している時期のみ、月1回ほど行います。水温が低すぎるとエアプランツにとって負担になるので、常温の水を使うようにしましょう。
害虫にも注意

エアプランツは害虫がつきやすい植物ではありませんが、乾燥した時にハダニなどが発生するケースもあります。ハダニは多湿に弱いですので、霧吹きで水を吹きかけることが予防になります。虫を見つけたときには、歯ブラシなどでこすり落としてください。
また、外に出しておくと外にいる虫に葉を食べられることもあります。基本的には室内で管理し、インテリアとして楽しみながら育てることをおすすめします。
置き場所や管理のコツ

エアプランツが育つ上で「風」は大事な要素です。特に水やりの後は蒸れることがないよう、風通しのいい場所で乾かしましょう。また、乾燥させすぎないように、冷暖房の風を直接当てないようにするなどの配慮も必要です。飾るときには、室内で自然の風が通る場所を選ぶといいでしょう。
エアプランツは原産地が温かい場所なので、寒すぎる場所は苦手です。年間通して室内の程よく明るく温かい場所で管理しましょう。20~30℃が適温とされており、10℃以下では育ちません。冬場は20℃を切らない程度に温度調整すると安心ですね。また、置き場所は温度の下がりやすい窓際を避けることも大切です。なお、直射日光は葉焼けする可能性があるので、レースのカーテン越しぐらいがちょうどいいとされています。
肥料や剪定の頻度

エアプランツの場合は、肥料も剪定も必須ではありません。ただし、いずれもタイミングよく行うことにより、生長を促す効果が得られます。エアプランツの生長を促したい、長持ちさせたいという場合は、必要に応じて肥料を与えたり剪定を行ったりするといいでしょう。おすすめの頻度や方法は下記の通りです。
- 肥料:生長期(春、秋)の水やりの際に行う。ミスティングやソーキング用の水に液体肥料を混ぜる(濃度は薄め)
- 剪定:葉が生長しすぎて変色した場合に行う。変色した部分をカットすることで、葉の密集を改善し通気性がよくなる
エアプランツのタイプによっては、剪定を行わないと葉が密集しすぎて通気性が悪くなりがちです。蒸れや変色の原因となるだけでなく、逆に水分が行きわたりにくくなり枯れてしまうことも。葉が細く伸び続けるタイプのエアプランツの場合は、特に状態をチェックして随時剪定を行うとより育ちやすくなるでしょう。
エアプランツがインテリアに向いている理由

エアプランツは管理がラクで見た目も個性的であることから、インテリアとしてよく使われています。加えて、土が要らないことも、気軽に取り入れやすい理由です。
土が必要な植物のデメリットは、土を室内に置くことによる衛生面の心配とインテリアとしての自由度の低さがあげられます。一方、エアプランツは、適度な水やりは必要なものの、置いても吊るしても貼り付けても飾れるので、さまざまな飾り方を楽しめるのが大きなメリットです。
エアプランツのおすすめの飾り方

5〜6㎝の小型種から80㎝を超える大型種まであるエアプランツ。ユニークなルックスですから、極端なことを言えば、置いておくだけでも存在感のあるインテリアになります。ですが、せっかく飾るのですから、もう少し手を加えて、よりおしゃれにしてみましょう。
ここでは、他の植物ではできない、エアプランツならではの飾り方をご紹介します。
ハンギング

エアプランツに麻紐などを巻いて、天井やカーテンレールから吊るしてみましょう。おしゃれなうえに、光・水・風というエアプランツにとって理想的な環境が整って一石二鳥です。長く伸びるウスネオイデスなどの品種だと、大きくボリュームのあるものに成長させることもできます。
ブリキや陶器などの器に入れて、マクラメ編みをした紐で吊るすのも、ナチュラルな雰囲気が出ておすすめです。また、スタイリッシュな感じが好きな人は、アイアンで作られたハンギングフレームを使うと、おしゃれ度が高まります。
ガラスに入れて

ガラスの器の中にカラーサンドや小石も一緒に入れて飾ると、爽やかなインテリアになります。置くだけでなく、ハンギングできる器もありますので、器選びも楽しんでください。1つだけでなく、高低差をつけて2つ3つと飾るのも素敵です。
大きめの器にエアプランツを2、3種類配置するのもいいですね。さらに、小さなフィギュアや雑貨も一緒に入れると、オリジナルの世界観も楽しめそうです。
流木などと合わせて

少し凝ったインテリアにしたい場合は、流木やウッドチップ、石などと合わせてディスプレイするのはいかがでしょう。夏には貝殻や白い砂、冬には赤い小物というように、添えるものを変えると季節感も出ます。
また、もともとの特徴を生かして、自然素材に着生させるのもいいですね。エアプランツが安定するように小さな穴をあけ、ワイヤーやひもなどで固定すると、自然に着生します。根が伸びてくると、エアプランツはより生育しやすくなり、大きくなる可能性が高まります。
エアプランツを増やしてみよう

エアプランツが順調に育つと、大きくなり子株が生長します。この子株を育てることで、エアプランツを増やしていくことができます。エアプランツを増やす一般的な方法は、「株分け」と「クランプ(群生)」の2種類です。
基本的には、小さい株を飾りたい場合は株分け、長期に渡って栽培し株を大きく育てたい場合はクランプ(群生)が選ばれることが多いようです。いずれにも異なるメリットや注意点があります。それぞれの特徴や手順を見ていきましょう。
株分け

エアプランツの株分けは、親株についた子株を外すだけでOKです。ただし、タイミングとやり方を間違えると失敗して枯れてしまうことも。成功させるポイントは、子株の大きさを見極めることと、子株を傷つけないように外すことです。子株が親株の3分の2ほどの大きさになったタイミングで、株分けを行いましょう。
手順
-
STEP. 1
親株の根元を片手で押さえ、反対側の手で子株を包むようにしっかりと持つ
子株を上手に外すために、両手を使います。
親株の根元から子株を切り離せるよう、しっかりと支えましょう。
-
STEP. 2
子株をゆっくりと倒しながら外す
子株を包んだ手をゆっくりと下におろすようにして、親株の根元から切り離します。
-
STEP. 3
完成
一つの株に複数の子株がついている場合、上記の手順を繰り返して一つずつ外していきましょう。
また、親株も子株に栄養を与える必要がなくなるため、エネルギーが温存されやすくなり長持ちが期待できる。
クランプ(群生)

子株を親株から切り離す株分けに対し、エアプランツに子株がついたまま増やす方法を「クランプ」といいます。品種によっては、株分けをせずに子株をつけたまま育てた方がいいものも少なくありません。下記のエアプランツは、比較的クランプしやすいといわれています。
クランプで増やす場合は、子株がついた状態で引き続き育てるだけですので、何か特別なことを行う必要はありません。ただし、子株が折れてしまうなどのトラブルが起きる場合もあるため、環境を整えておくことは重要です。また、クランプにより葉が密集すると、以前よりも蒸れやすくなる、水やりをしたときに水分が行きわたりにくくなるなど、配慮が必要な状態になる点にも注意が必要です。
- 安定した場所で管理する(子株が折れないようにするため。株を固定する方法もおすすめ)
- 水分を全体に与える(密集した葉の中心部にも水やりを行う)
- 通気性を確保する(枯れた葉をこまめに取り除く、水やり後は風を当てて内側までしっかりと乾燥させる)
子株が育つと親株は衰退し、生長しなくなります。親株が枯れたら、そのままにせずに取り除いた方が子株が育ちやすくなります。また、複数の子株がすべて順調に育つとは限りません。中には小さなうちに枯れてしまうものもあるでしょう。その場合も、枯れたものをつけたままにしておくのはNG。通気性が悪い状態が続き、元気な株まで傷む原因になってしまいます。
クランプで増やすエアプランツのお世話は長期に渡るため、枯れたものをこまめに取り除きながら元気な状態を維持しましょう。長く育てる間に様々な変化が見られ、世代交代していくエアプランツ。愛着もより一層湧いていくのではないでしょうか。
まとめ
エアプランツの基本情報や育て方のポイント、飾り方のアイデア、さらに増やし方までお伝えしてきました。エアプランツの生態や基礎知識を押さえておくと、育てることを楽しみつつ、インテリアに上手に取り入れることができそうですね。グリーンを使った遊び心のある部屋づくりを楽しみたい人には、ぴったりな植物だといえるでしょう。
さらに、インテリア雑貨や小物と一緒に飾ると、ワンランク上のおしゃれな部屋を目指せそうです。たくさんの種類のエアプランツがありますので、好みの形や色のものを探してみてください。
- エアプランツは種類が豊富で、管理が楽なので育てやすい植物
- 水やりや害虫、置き場所、温度管理、増やし方など、基礎知識を持って育てよう
- 土が要らない特長を生かして、おしゃれに飾って楽しもう